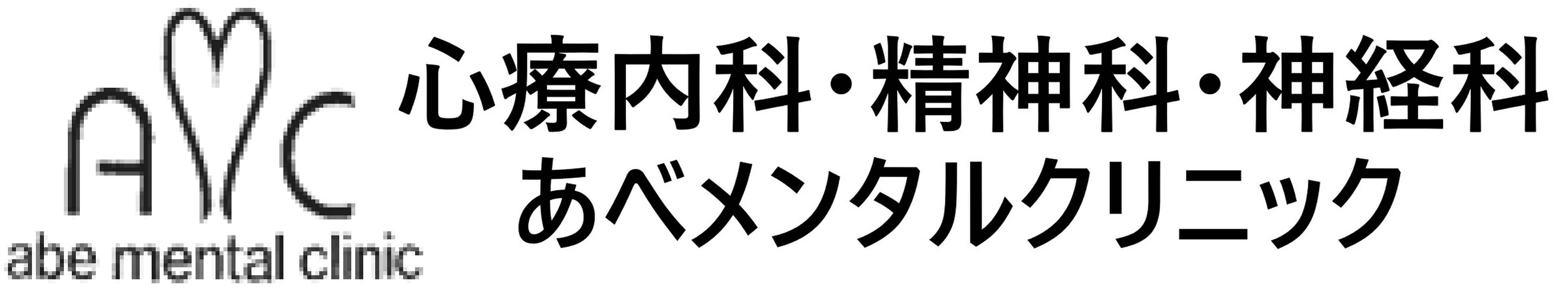統合失調症
統合失調症について詳しく解説します
どんな病気か
統合失調症は、考えや気持ち、行動がまとまりにくくなる精神疾患です。こころや考えの「統合」が「失調」する状態、と表現されることもあります。この病気にかかると、現実と非現実の区別がつきにくくなったり、幻覚や妄想といった症状が現れたりすることがあります。
約100人に1人がかかると言われており、決して珍しい病気ではありません。多くは思春期から青年期(10代後半~30代)に発症しますが、適切な治療とサポートによって、症状をコントロールし、その人らしい生活を送ることが可能です。
かつては「精神分裂病」と呼ばれていましたが、病名に対する誤解や偏見を招きやすいことから、2002年に「統合失調症」へと名称が変更されました。
主な症状
統合失調症の症状は多彩で、大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けられます。症状の現れ方や程度は人によって様々です。
陽性症状(本来ないはずのものが出現する症状)
- 幻覚:実際にはないものをあるように感じること。周りの人には聞こえない声が聞こえる「幻聴」が最も多い。
- 妄想:明らかに誤った内容を信じ込み、周りが訂正しようとしても受け入れられない考え。「誰かに悪口を言われている」「監視されている」「狙われている」といった被害妄想や、「自分は特別な力を持っている」といった誇大妄想などがある。
- 思考の混乱:考えがまとまらず、話が支離滅裂になったり、会話の途中で話が飛んだりする。
- 奇異な行動:興奮して大声を出したり、独り言を言ったり、不可解な行動をとったりする。
陰性症状(本来あるはずの機能が低下・消失する症状)
- 意欲の低下:何事にもやる気が起きない、根気が続かない、身の回りのことに関心がなくなる。
- 感情の平板化(感情鈍麻):喜怒哀楽の表現が乏しくなり、表情が硬くなる、感情の起伏が少なくなる。
- 思考の貧困:考えが浮かばない、会話の内容が乏しくなる。
- 社会的引きこもり:人との関わりを避け、自室に閉じこもりがちになる。
陰性症状は、うつ病の症状や、単なる怠けと間違われることもありますが、病気の症状として現れている可能性があります。
認知機能障害(記憶・注意・判断力などの低下)
- 注意・集中力の低下:物事に集中できない、気が散りやすい。
- 記憶力の低下:新しいことを覚えられない、過去の出来事を思い出せない。
- 遂行(実行)機能の低下:計画を立てて物事を実行することが難しい、臨機応変な対応が苦手。
- 判断力の低下:物事を適切に判断することが難しい。
これらの認知機能の低下は、学業や仕事、日常生活を送る上で困難を引き起こす原因となります。
原因
統合失調症の原因はまだ完全には解明されていませんが、一つの原因ではなく、複数の要因が複合的に関与して発症すると考えられています。「脆弱性ストレスモデル」という考え方が一般的で、生まれ持った脳の機能的な脆弱性(病気になりやすさ)に、心理的・社会的なストレスが加わることで発症の引き金になるとされています。
- 生物学的要因: 脳内の神経伝達物質(特にドーパミンやグルタミン酸など)のバランスの乱れ、脳の構造や機能の変化が関与していると考えられています。遺伝的な要因も発症リスクに関係しますが、遺伝だけで決まるわけではありません。
- 環境要因: 人間関係のストレス、ライフイベント(進学、就職、結婚など)、生活環境の変化などが発症のきっかけとなることがあります。
親の育て方や本人の性格が直接の原因ではありません。
治療について(当院でのアプローチ)
統合失調症の治療は、症状をコントロールし、再発を防ぎ、その人らしい生活を送れるようになること(リカバリー)を目指します。治療の柱は「薬物療法」と「心理社会的療法」です。あべメンタルクリニックでは、患者さまやご家族と協力しながら、継続的な治療とサポートを行います。
- 薬物療法: 主に抗精神病薬が用いられます。抗精神病薬は、特に幻覚や妄想などの陽性症状を改善し、再発を予防する効果があります。近年では、副作用が比較的少ない非定型抗精神病薬が主流となっています。症状を安定させるためには、医師の指示に従って薬を継続して服用することが非常に重要です。自己判断で中断すると再発のリスクが高まります。副作用について心配な場合は、必ず医師にご相談ください。
-
心理社会的療法: 薬物療法と並行して行われる重要な治療法です。様々なアプローチがあります。
- 心理教育:本人や家族が病気について正しく理解し、対処法を学ぶ。
- リハビリテーション:認知機能の改善を目指す訓練(認知機能リハビリテーション)や、生活技能・対人関係スキルを向上させる訓練(SST:ソーシャルスキルトレーニングなど)。
- 作業療法:軽作業やレクリエーションなどを通じて、集中力や持続力、対人関係能力の回復を目指す。
- 精神療法:支持的な関わりを通じて、悩みや不安の軽減を図る。
- 家族支援:家族が病気を理解し、本人への適切な関わり方を学び、家族自身の負担を軽減するためのサポート。
- 休養と環境調整: ストレスを避け、十分な休養をとることも大切です。安心して過ごせる環境を整えるためのアドバイスを行います。
統合失調症は、早期に発見し、適切な治療を継続することが、回復にとって非常に重要です。
こころや考えの不調を感じたら
「周りの人に聞こえない声が聞こえる」「誰かに見られている気がする」「考えがまとまらない」「やる気が出ない」など、ご自身やご家族のことで気になる症状があれば、一人で抱え込まずにあべメンタルクリニックにご相談ください。早期の対応が回復への鍵となります。
ご予約・お問い合わせはこちら