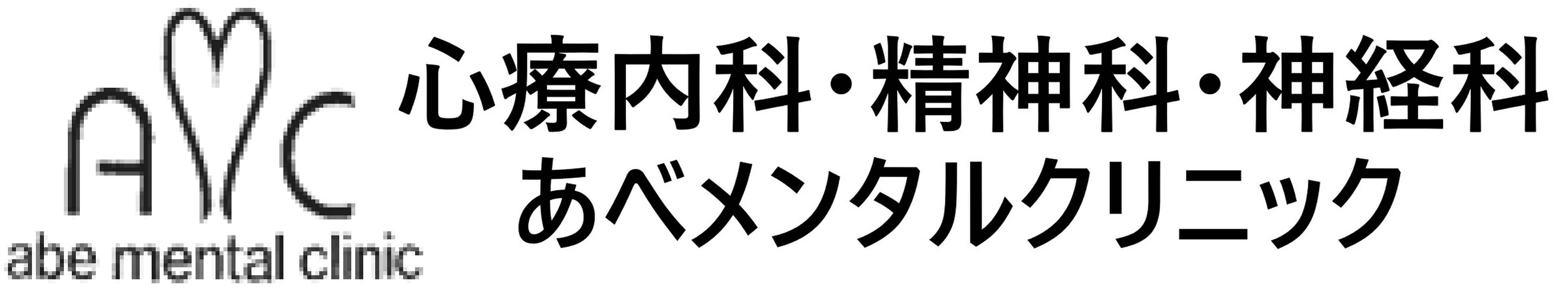不安障害
不安障害について詳しく解説します
どんな状態か
不安は、危険や脅威に対して私たちが自然に感じる感情ですが、その不安が過剰になったり、特定の状況や対象に対して強すぎる恐怖を感じたりして、日常生活に支障をきたしてしまう状態を「不安障害(不安症)」と呼びます。
不安障害にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴的な症状が現れます。代表的なものには、特定の理由なく過剰な心配が続く「全般不安障害」、突然強い不安発作(パニック発作)に襲われる「パニック障害」、人前で過度に緊張したり注目されることを恐れたりする「社交不安障害(社交恐怖)」、特定の物や状況(高所、閉所、動物など)に強い恐怖を感じる「特定の恐怖症」などがあります。
主な症状
不安障害の症状は、タイプによって異なりますが、共通してみられる精神症状と身体症状があります。
精神症状
- 過剰な心配、漠然とした不安感
- 恐怖感、パニック発作(強い恐怖とともに動悸、息切れ、めまい、吐き気などが起こる)
- 人前での強い緊張、恥ずかしさ、赤面、発汗
- 特定の物や状況に対する強い恐怖と回避
- 落ち着きのなさ、いらいら感、集中困難
- 「また発作が起きるのではないか」という予期不安
身体症状
- 動悸、胸の圧迫感、息苦しさ
- めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ
- 吐き気、腹部の不快感、下痢
- 体の震え、発汗、手足の冷え
- 筋肉の緊張、肩こり、頭痛
- 疲労感、不眠
原因
不安障害のはっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複合的に関与していると考えられています。
- 生物学的要因: 脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、GABAなど)のバランスの乱れや、特定の脳部位(扁桃体など)の機能異常が関与すると考えられています。遺伝的な要因も指摘されています。
- 心理的要因: ストレスの多い出来事(仕事、人間関係、経済問題など)、過去のトラウマ体験、物事に対する認知の歪み(悲観的思考、破局的思考など)、心配性などの性格傾向が影響することがあります。
- 環境要因: 幼少期の環境や、現在の生活環境なども発症に関わることがあります。
治療について(当院でのアプローチ)
不安障害の治療は、タイプや重症度に応じて、精神療法と薬物療法を組み合わせて行うことが一般的です。あべメンタルクリニックでは、患者さまの状態を丁寧に見極め、適切な治療計画を立てていきます。
- 精神療法(心理療法): 不安を引き起こす考え方や行動パターンを見直し、対処法を身につけることを目指します。特に認知行動療法(CBT)は、不安障害に対する有効性が示されています。特定の恐怖や回避行動に対しては、段階的に不安な状況に慣れていく曝露療法(エクスポージャー)が行われることもあります。
- 薬物療法: 症状を和らげ、精神療法に取り組みやすくするために薬物療法を行います。主に抗うつ薬(SSRIやSNRIなど)が用いられます。これらの薬は不安感を軽減する効果も期待でき、依存性が少ないため比較的長期間使用できます。即効性のある抗不安薬(ベンゾジアゼピン系など)は、強い不安発作時などに頓服として用いることがありますが、依存性に注意が必要なため、医師の指示のもと慎重に使用します。
- リラクゼーション法: 呼吸法や自律訓練法などのリラクゼーション法を習得し、不安や緊張を自分でコントロールする方法を学ぶことも有効です。
- 環境調整: ストレスの原因となっている環境要因があれば、その調整について一緒に考えます。
不安障害は治療によって改善が期待できる病気です。早めに専門医に相談し、適切な治療を開始することが大切です。
過剰な不安、ひとりで抱え込まないで
「いつも心配事が頭から離れない」「人前に出るのが怖い」「突然の動悸や息苦しさに襲われる」など、過剰な不安によって日常生活に支障を感じている方は、ぜひあべメンタルクリニックにご相談ください。
ご予約・お問い合わせはこちら