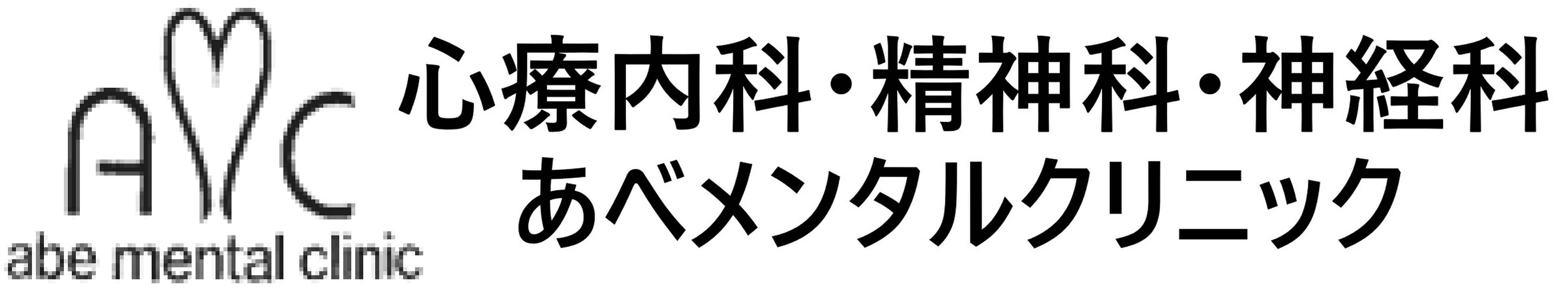適応障害
適応障害について
どんな状態か
適応障害は、仕事、学業、家庭環境、人間関係など、生活の中で起こる特定の出来事や状況(ストレス因)に対して、著しい苦痛を感じたり、そのために日常生活や社会生活(学業や仕事など)に支障が出たりする状態を指します。
原因となるストレス因がはっきりしており、そのストレス因が始まってから通常3ヶ月以内に症状が現れます。症状の種類や程度は人によって様々ですが、その苦痛や機能障害は、一般的に予想されるストレス反応の範囲を超えている場合に診断されます。
ストレス因がなくなれば症状は改善することが多い(通常6ヶ月以内)ですが、ストレス因が続く場合や、うまく対処できない場合には症状が長引くこともあります。うつ病など他の精神疾患とは区別されますが、早期に対応することが大切です。
主な症状
適応障害の症状は、ストレスに対するこころやからだ、行動面の反応として現れ、非常に多様です。代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
精神症状の例
- 気分の落ち込み、憂うつな気分、涙もろさ
- 不安感、過剰な心配、神経過敏、緊張感
- イライラ感、怒りっぽさ
- 意欲や集中力の低下、何かを決めるのが難しい
- 絶望感、どうにもならないという感覚
身体症状の例
- 睡眠障害(不眠、過眠)
- 食欲不振または過食
- 疲労感、倦怠感、体が重い
- 頭痛、肩こり、腹痛、動悸、めまいなどの身体的不調
行動面の症状の例
- 無断欠勤、遅刻、学業成績の低下
- 引きこもり、人との交流を避ける
- (特に青少年で)喧嘩、無謀な運転、物を壊すなどの問題行動
- 過度の飲酒
これらの症状が、ストレス因との関連で現れ、社会生活や職業・学業上の機能に著しい障害を引き起こしている場合に、適応障害の可能性が考えられます。
原因
適応障害の直接的な原因は、明確な「ストレス因」です。これは、単一の出来事(例:失恋、転職、転居、病気)の場合もあれば、複数の出来事や持続的な状況(例:人間関係の問題、経済的な困難、慢性的な病気)の場合もあります。
ただし、同じようなストレスを経験しても、誰もが適応障害になるわけではありません。発症には、以下のような要因が影響すると考えられています。
- 個人の脆弱性: その人が元々持っているストレスへの対処能力(コーピングスキル)、性格傾向、過去の精神的な問題の経験などが影響します。
- サポートシステム: 家族や友人、同僚など、周囲からのサポートが得られやすいかどうか。
- ストレス因の性質: ストレス因の強さ、持続期間、予測可能性なども関与します。
適応障害は、本人の「弱さ」や「甘え」の問題ではなく、ストレス因と個人の要因との相互作用によって生じる状態です。
治療について(当院でのアプローチ)
適応障害の治療目標は、ストレス因への対処能力を高め、症状を軽減し、社会生活への適応を回復することです。当院では、以下の点を中心にサポートを行います。
- 環境調整とストレス因への対処: 可能であれば、ストレスの原因となっている環境を調整します。また、ストレス因への対処方法(問題解決技法など)を一緒に考えます。
- 精神療法(カウンセリング): ストレスへの対処能力を高めたり、物事の捉え方を見直したりするために、支持的な精神療法やカウンセリングが有効です。
- 薬物療法: 不眠、不安、抑うつなどの症状が強い場合には、症状を和らげるために補助的に薬物療法(抗不安薬、抗うつ薬、睡眠薬など)を行うことがあります。ただし、薬物療法は根本的な解決策ではなく、対症療法として用いられます。
- 十分な休養: 心身の回復のためには、十分な休息をとることが重要です。
原因となるストレス因が取り除かれたり、本人がうまく適応できるようになると、症状は改善していくことが一般的です。早期に適切なサポートを受けることで、回復を早め、症状の慢性化や他の精神疾患への移行を防ぐことにつながります。
環境の変化などでつらさを感じていませんか?
職場や学校、家庭環境の変化など、特定の出来事の後から気分が落ち込んだり、不安が強まったり、普段通りの生活が送れなくなったりしていませんか?それは適応障害かもしれません。一人で悩まず、あべメンタルクリニックにご相談ください。原因となっているストレスやご自身の状況を整理し、回復への道筋を一緒に見つけていきましょう。
ご予約・お問い合わせはこちら